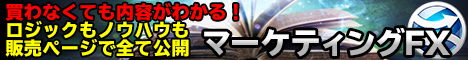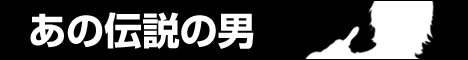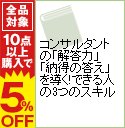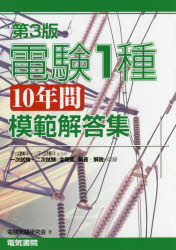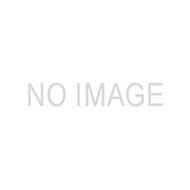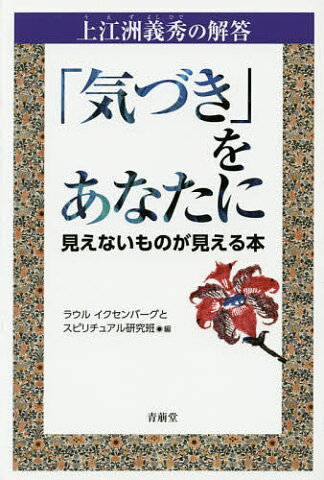解答の通販・作り方の特集、いくつ持っていても助かる商品だから安く買えたらうれしいですね
こんにちは!
��ら2nで
あまりに解答的
問15。
問 15 道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
車両の運転者が道路交通法第 66 条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により A ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る B が当該車両につき過労運転を防止するため必要な C を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するためD ことを指示することができる。
A 1.運転の維持、継続 2.正常な運転
B 1.車両の使用者 2.車両の所有者
C 1.運行の管理 2.労務の管理
D 1.必要な施設等を整備する 2.必要な措置をとる
答えは
A 2.正常な運転
B 1.車両の使用者
C 1.運行の管理
D 2.必要な措置をとる
26年1回にも出題されています。
引用します。
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る( B )が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( C )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため( D )ことを指示することができる。
A 1.運転の継続 2.正常な運転
B 1.車両の所有者 2.車両の使用者
C 1.運行の管理 2.労務の管理
D 1.必要な措置をとる 2.休憩・仮眠等の施設を整備する
答えは。
正解 A2 B2 C1 D1
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により(正常な運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る(車両の使用者)が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(必要な措置をとる)ことを指示することができる。
この問題は過去、24年2回試験にも出題されています。
何度も出題されています。
————————————
キャンペーンのご案内。
4月5日、6日、7日の3日間だけのチャンスです。
50%off早割キャンペーンを実施します。
この価格での実施は最後になります。
3日限りです。
前回お申込みができなかった方は最後のチャンスとなります。
お見逃しなく!
早期に準備を始めれば合格する確率は格段に上がります。
寺子屋塾合格講座は
「ラーニングボックス」はクイズ形式で習得できる演習です。
過去問10回分がすぐ始められます。
年度別過去問演習
ブランクを埋める問題(27年1回-29年1回)
暗記法
実際の講座では過去問をスマホでいつでもどこでも何回でも繰り返しできます。
すぐにスタートできます。
解答のことならなにからなにまでおまかせサイト♪
「気を抜くな!気を抜いたら、信長のように攻められるぞ!」
塾の先生の口癖でした。
テンちゃんの場合は信長ように天下を取ったわけではないので、
「信長(に支えていた足軽)のように」
が、正しい例えですけど・・・。
で、この言葉、どんな時に言われていたかと言うと、
「解答用紙はわからなくても必ず埋めること!何度も言ってるよね。どうして埋めないの?埋めないのは気を抜いてる証拠だよ。気を抜くな!気を抜いたら、信長のように攻められるぞ!」
と、なります。
で、テンちゃんは反論します。
「でも、答えがわからないのに書けないです」
「どうせ間違っているってわかっているのに、書く意味がわかりません」
そこを何度説明しても、自分で納得していないから、「書かなきゃいけないらしい」と思っていても、わからない問題だから後回しにして、最終的には書くことを諦めてしまう。
そう言うことが何度も続きました。
ひどい時には、選択問題を埋めてないと言うことが何度も。
へ?
大人にとっては、へ?なんですけど、本人にしてみれば、
「だってわからないから」
「なんで?ただの選択問題でしょ?A.B.C.Dの中から一つ選べばいいだけでしょう?考えなくていいんだよ、どうせわかんないんだから。どれか一つ選べばいいだけじゃん」
「それで合っていても意味ないじゃん。本番じゃないんだから」
「本番で忘れないためにも今、ちゃんとやらなきゃダメなんじゃん」
「本番ではちゃんとやるよ」
「今、埋める習慣をつけとかないと本番でも忘れるんだよ!だからちゃんと埋めろっつってんの!」
「本番ではやるって」
「だったら今、やれってんだよ!埋めろって言われたらつべこべ言わず埋めろ!」
よく奥さんキレてました〜。
それでも、テンちゃん、その癖、なかなか治りませんでした。
結局、本番までその不安は拭えませでしたから。
渋々の試験本番の様子、今でも覚えています。
雪の中、渋々の試験会場に向かっている途中、塾の先生が三人もテンちゃんを待ってくれていました。
その中の一人の若い女の先生がテンちゃんの両手を包み込むように握って、
「テンちゃんだったら大丈夫!今までやってきたことを普通にやれば受かるから」
「うん」
「絶対大丈夫だから!最後まで諦めない。絶対に解答用紙は全部埋める。空欄を全て無くす。わかってるよね?」
「うん」
「油断したら、信長のように攻められるよ」
そうそう、信長のくだりを言っていたのはこの先生です。
「うん。絶対に埋める」
そう言いながら涙ぐむテンちゃん。
おいおい。泣くのは受かってからにしてくれよ〜。
結局、悔し涙になってしまったわけですが・・・・・。
悪い癖を治すのは、簡単ではありません。
テンちゃんに言わせれば、
「わからない問題の答えを適当に書くのは嫌だ!」
て、ことなのかもしれませんが、実のところ、おそらくそれは言い訳で、
わからない問題の答えを書かない。空欄を埋めない。と言うことは、諦めていると言うことです。
わからなくても、適当でも、空欄を埋めると言うことは、最後まで諦めないと言うことです。
「適当でもなんでも埋めるぞ!書くぞ!」
そう思えて、書こうとする限りは、考え続けます。
なぜなら、
書くからには間違えたくない!
だから、時間ギリギリまで考える。
それを模試の段階から確実にできるようにする。
我々、大人からしてみれば当たり前に思えることも、子供の立場になると、当たり前ではなかったりするから、厄介なのです。
そう言うところを見落とすと、我が家のように命取りになります。
一番合格の可能性が高かった2月1日の渋々を落とした原因はわかりません。
単純に学力不足だったのかもしれません。
ただ、
「数学で全部埋めることができなかったから」
と、テンちゃん自身が思っているということが、彼女の後悔をより大きなものにしているということです。
後悔先に立たずです。
最後まで読んでくださってありがとうございました。
解答に現代の職人魂を見た
こんにちは![]()
文科1類1年の KUMOKI です![]()
今回は地理の勉強法を紹介します。
地理は社会科の中で
覚える知識が歴史に比べて少ない教科だと言われています。
地理の対策を始めるのが遅い人も多いですし、
参考書や問題集が日本史・世界史に比べて少ないですが、
本番の得点源にすることができます。
だから決して疎かにせず、ぜひ得意科目にしてください![]()
![]()
地理では、知識系の問題だけではなく、
図表の読み取りなどで正しく知識を使う考察系の問題も多いです。
知識をつけると同時に、知識を正しく使いこなすことが特に要求されます。
勉強したばかりの時は、知識を正しく使いこなせず、
点数が伸び悩むこともあります。
勉強してるのに点数が出ないので、心が折られそうになるのですが、
あと一歩なのでここで諦めないことが大事です![]()
諦めずに教科書や参考書を何度も熟読して知識を定着させ、
過去問を繰り返し解き、
地図帳で知識を使った読み取りのための着眼点を身につければ、
点数は必ず取れるようになります。
知識が比較的少ないということは、反復しやすい教科であるということだと私は考えています。
次に、知識をつける上で大切だと思うことを書きます![]()
![]()
頻出の国以外の個々の国や都市の特徴を押さえるときりがないので、
汎用性の高い知識を身につけることを心がけてください。
例えば、発展途上国、人口大国、熱帯、工業地域といった
国や地域に共通する特徴をしっかり覚えてください。
センター試験を含むマーク式の問題は、
特徴を理解しているかを問うものが多いからです。
2次試験で出題される論述問題では、赤本などを見れば分かると思うのですが、
要求されている論述のポイントの数が字数から分かります。
それに従って知識をアウトプットして解答にすれば、点を取れるようになります。
また、東大地理に関していうと、近年記述量が大幅に増加しています。
そのため、問題を見て論述のポイントを短時間でひねり出す訓練も大切です。
以上、地理の勉強法でした![]()
ぜひ参考にしてみてください![]()
![]()